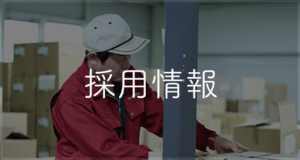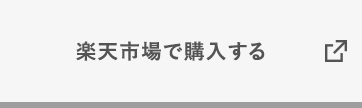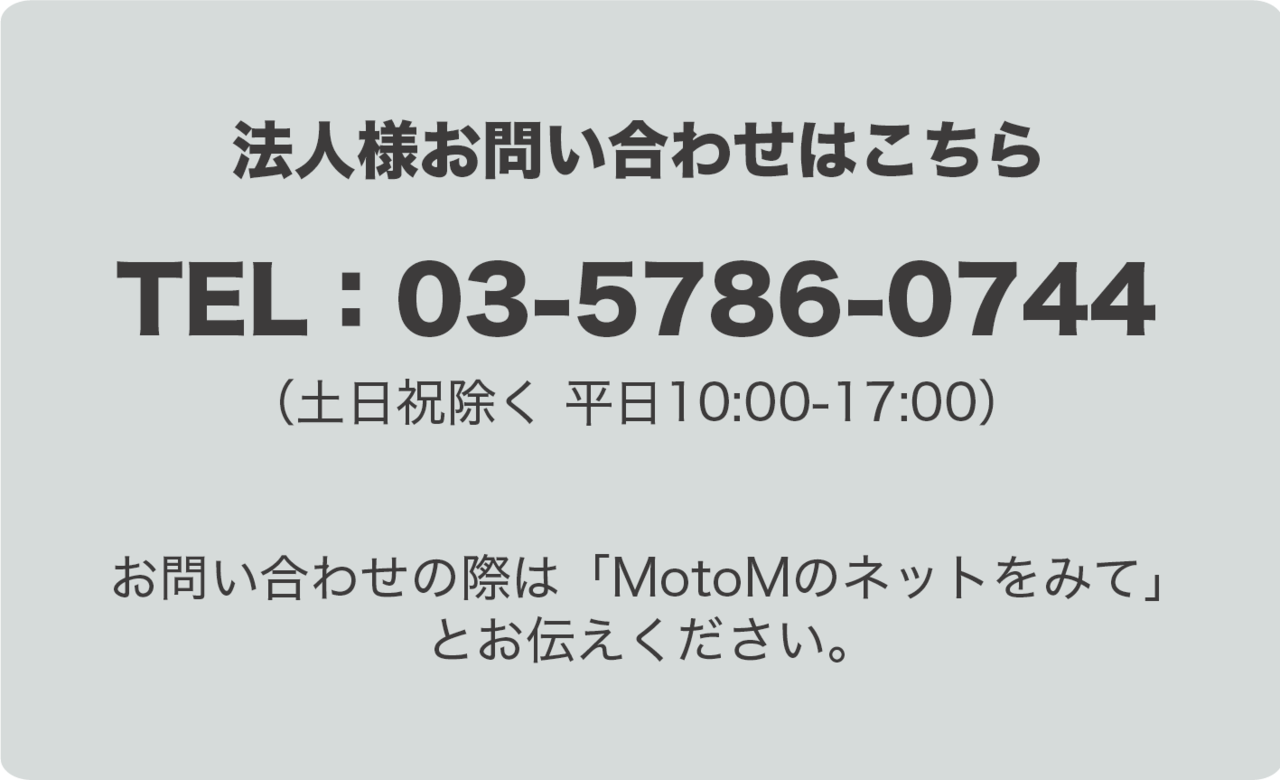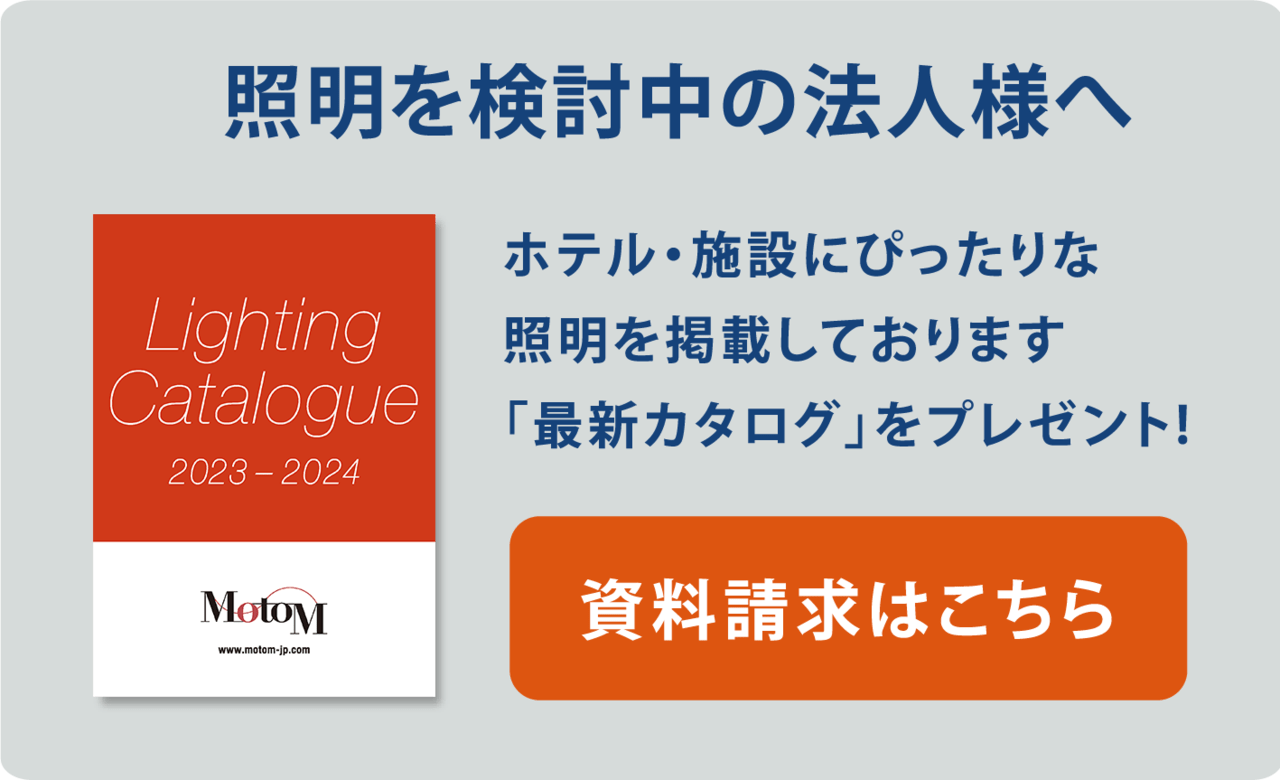購入した製品にトラブルが起きた時に、どんな対応をしているでしょうか。
多くの場合、保証期間内ならメーカーのサポートを受けるため、購入先のお店かまたはメーカーのサービスセンターに連絡しているのではないでしょうか。
万が一そのトラブルが原因で、何らかの損害が発生したらどうでしょうか。
損害の大小で対応が異なるかもしれませんが、その場合はPL法による対応を考えた方がよいでしょう。
この記事ではPL法について紹介しています。
万が一の時に備えて、消費者を守ってくれる仕組みを理解しておくと安心です。
目次
PL法とメーカー保証期間の関係について知っておきたい基本と実務ポイント
PL法(製造物責任法)とメーカー保証期間の関係は、消費者にとって安心して製品を使用するための重要なポイントです。ここでは、両者の基本的な考え方や、その違い、そして実際の対策について、以下の点を箇条書きで整理しました。
PL法の基本と役割
製品に起因する事故や損害が発生した場合、製造者や販売者がその責任を負う法律です。
対象範囲
製造過程や設計上の欠陥、表示の不備などに起因する事故に対して適用されます。
消費者保護
消費者が安心して製品を利用できるよう、損害賠償請求の根拠となる法的枠組みが整備されています。
メーカー保証期間の基本と特徴
保証期間の設定
製品の初期不良や短期間で発生する不具合に対する補償期間として設けられ、各メーカーが独自の基準で定めています。
保証対象
一定期間内に発生した不具合や故障に対して、無償修理や交換、返金などの対応が行われます。
消費者のメリット
保証期間中は、万が一のトラブル時にメーカーに対して迅速に対応を求めることができ、安心感が得られます。
PL法とメーカー保証期間の関係性
補完的な役割
メーカー保証は、あくまで事前に設定された一定期間内の不具合に対する対応であり、PL法はその期間外に発生した損害にも適用される場合があるため、両者は補完的な関係にあります。
保証期間の限界
保証期間が終了した場合でも、製品に起因する事故や損害については、PL法に基づいて損害賠償請求が可能です。
法的手続きの違い
保証期間内はメーカーとの直接交渉が基本ですが、保証期間外の場合は、PL法に基づく法的手続きが必要となる場合があります。
消費者が知っておくべき実務ポイント
契約内容の確認
製品購入時の保証書や契約書に記載されている保証内容と期間を必ず確認し、PL法との違いを理解することが重要です。
トラブル発生時の対応策
保証期間内なら、まずメーカーへの連絡や保証書の提示を行い、無償修理や交換を依頼する。
保証期間外の場合は、PL法に基づく損害賠償請求の可能性も含め、消費生活センターや弁護士への相談を検討する。
情報収集の重要性
最近の判例や消費者団体の情報をもとに、PL法の適用事例や最新の保証制度の改訂内容を把握しておくと、トラブル回避に役立ちます。
今後の製品選びと
保証の視点
製品購入前に、メーカー保証の内容と保証期間、そしてPL法がどのように補完するかを確認することは、購入後の安心感を大きく左右します。
企業側も、保証内容の充実だけでなく、PL法に基づくリスク管理を徹底することで、信頼性向上を図る必要があります。
PL法とは?メーカー保証期間とは?

PL法のPLとはProduct Liabilityの頭文字を取った呼び名で、正式名称は「製造物責任法」と言います。
この法律は平成7年(1995年)に施行された法律で、消費者が欠陥製品に起因する損害賠償を製造業者へ請求するルールを定めたものです。
PL法施行の背景
この法律が出来た背景には、それまでは消費者(被害者)が製造業者へ損害賠償請求することが非常に困難であったためです。
民法の「不法行為法」では、欠陥品によって受けた損害の賠償請求を行うには、まずは被害者が製造業者に不法行為があったことを証明する必要がありました。
また「不法行為責任」が生じるのは、製造業者に過失があった場合のみとなります。
従って、被害者が欠陥が生じた理由を追求し、相手の過失を立証しなければ救済を受けられませんでした。
そして実際に裁判をするとなると、時間とお金がとてもかかる上、勝つ見込みも厳しくて、極めて被害者に不利な状況でした。
そこで政府はPL法を施行することにより、製造者に「不法行為責任」ではなく「製造物責任」を負わせることにしました。
この法律によって、被害者は「過失」ではなく「欠陥」を証明出来れば、損害賠償請求が可能となりました。
「製造物」の定義
それでは、PL法を具体的に見て行きましょう。
先ず、「製造物」の定義について説明します。
この法律の「製造物」の要件は、①動産であること、②製造又は加工されていること、の 2 点です。
➀動産であることより、「土地」「建物」等の不動産、そして「電気」「熱」「音」等の無体物は製造物とはなりま せん。
注意点として、「空気」「ガス」「蒸気」等の気体は有体物であり、製造物に含まれます。
もう1点、コンピューター等を動かす「ソフトウェア」は注意が必要です。
ソフトウェア自体は無体物ですが、ソフトウェア が組み込まれたハードウェアは製造物であり、ソフトウェアの不具合が製造物自体の欠陥となる場合があります。
②製造又は加工されていることより、人の手が加わったあらゆるものが対象となります。
家電製品から、人形、自転車、机や椅子、弁当やお菓子などの食料品まであらゆる分野の製品が該当します。
一方、野菜や果物、魚まるまる一匹など、一切手を加えていない商品については適応除外となります。
「欠陥」の定義
この法律において「欠陥」とは、製品が通常有すべき 安全性を欠いていることをいいます。
「製造上の欠陥」「設計上の欠陥」「指示・警告上の欠陥」があるとされ、この法律ではこれらすべてを含みます。
但し、あくまで「欠陥が予測出来た場合のみ」という前提があり、「当時の科学技術では危険性が予見できなかった」場合には免責となります。
「製造業者」の定義
この法律では、製造、加工業者に加え、輸入業者も「製造業者」に含まれます。
例えば、個人でアクセサリーを作って販売した場合も、この法律の適応を受けます。
輸入品については、製造に一切係っていない場合でも、輸入販売を行っただけで責任を負うことになります。
また、製造者でなくとも、製造会社と誤認される様な表示がされていた場合や、実質的に製造者の立場にあるだけで、責任を問われることになります。
以上のように、PL法は消費者第一の法律であり、製造者にとっては非常に厳しい内容となっています。
メーカー保証期間とは
メーカー保証とは、製造業者が製品自体の品質を保証することを言います。
保証期間は、販売後の一定期間の保証をつけることで、消費者に安心と製品の優位性をアピールするものです。
保証期間は製品によって異なり、家電で1~2年、家具で5年、住宅で10年など、故障しやすい物や買い替えのサイクルが早いものほど短くなる傾向です。
保証の内容は、「通常の方法で使用した製品が保証期間内に故障した場合に、製品を無償で修理または交換する」というものが一般的です。
家電量販店等では、メーカー保証期間に販売店独自の保証期間をプラスして消費者にアピールする、保証延長を行っています。
その実態は、メーカー保証が切れた製品の有償修理費用を家電量販店が負担しています。
なお、製品に製造上の欠陥がある場合は、保証期間が過ぎても無償で修理に応じたり、状況によっては自主的に製品を回収することもあります。
メーカー保証期間が過ぎてもPL法で損害賠償請求ができる

PL法は、メーカー保証期間が過ぎてから損害を受けた場合でも、購入してから10年間までは損害賠償請求が行えます。
但し、実際に損害を受けた場合、その事実を知った時点から3年で時効となります。
従って、購入してから10年以内の製品の欠陥で損害を受けた場合は、次の2点を抑えておけば大丈夫です。
製品に欠陥があること
欠陥とは、「製造上の欠陥」「設計上の欠陥」「指示・警告上の欠陥」のことです。
製造上の欠陥:製造物が設計仕様通りに作成されていない為、安全性に欠けるもの
設計上の欠陥:設計自体に問題がある為、安全性に欠けるもの
指示・警告上の欠陥:取扱説明書の記述に間違いがあり、正しい使い方を説明してい
ないもの
間違った使い方をすることで危険が及ぶことを説明していないもの
その欠陥によって受けた被害との因果関係を証明できること
因果関係を自分で証明できない場合は、専門業者に依頼して対応しましょう。
業者の費用も含めて損害賠償請求が可能です。
PL法の時効は10年、保証期間後も補修部品は10年ストック

PL法では製品を購入してから10年で除訴(時効)となります。
そのため、製造業者は製品の販売を終了した時点から10年程度補修部品をストックしておくと、万が一の場合に対応ができます。
製品寿命が極めて短い製品では、部品のストックよりも製品を最新型に交換するという対策もあるでしょう。
いずれにせよ、消費者から欠陥を指摘され、被害との因果関係を証明された場合は速やかな対応が求められます。
場合によってはマスコミ対応なども必要になるでしょう。
またネットで拡散することも十分考えられます。
消費者は、時として想定外の使い方をする場合があります。
製品の取扱説明書が禁止事項などを全て網羅できるわけではないので、製造業者は何時でも非常時の対応ができる体制を整えておかなくてはなりません。
まとめ
PL法は消費者の立場を最大限配慮しており、製造業者および輸入業者にとってはとても厳しい法律です。
良い製品、革新的な商品を他社に先駆けて市場投入することは、ビジネスでは当然の戦略です。
PL法のおかげで、メーカーは可能な限り製品のチェックをし、万全の状態で発売するでしょうから、新製品を安心して購入すればよいでしょう。

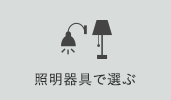
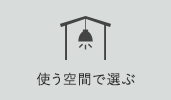
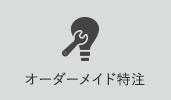
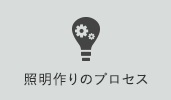

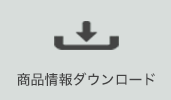

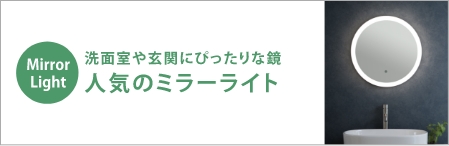

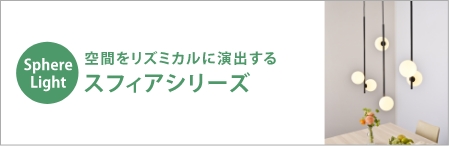








![サビ風黒色塗装ワークライト[MST023]](https://www.motom-jp.com/wp-content/uploads/2022/03/mst023s.jpg)















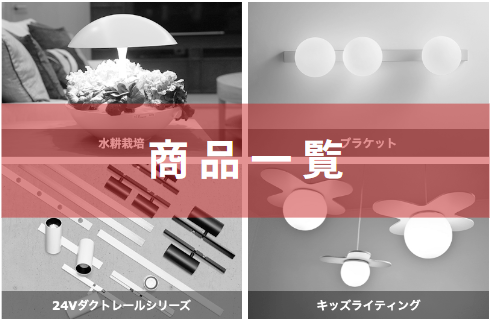

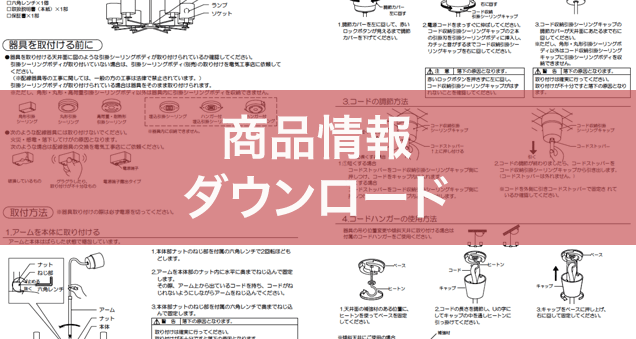
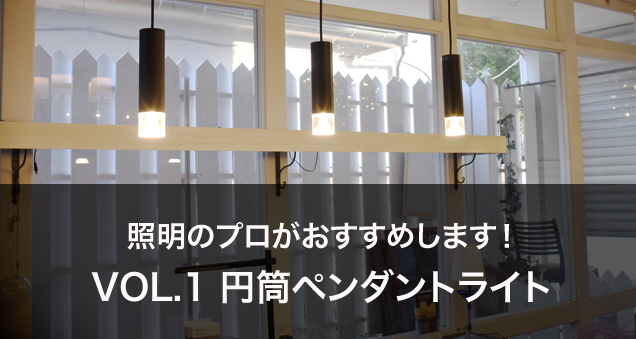
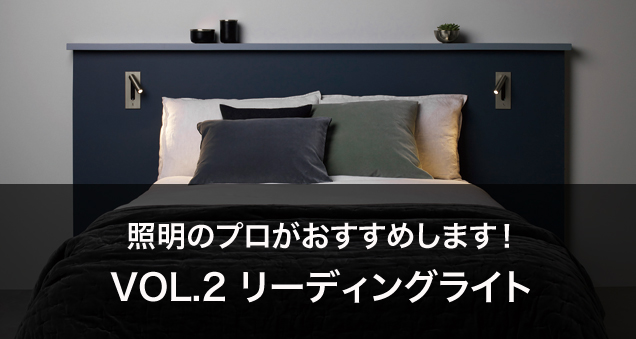
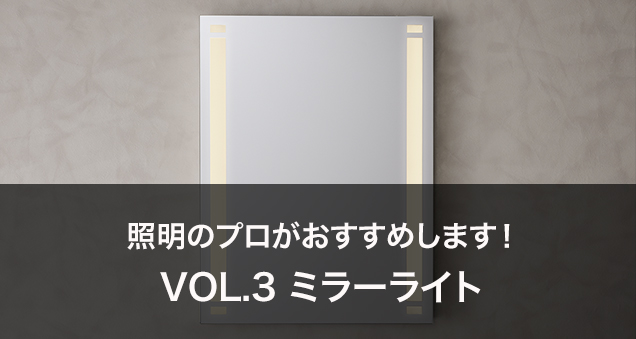
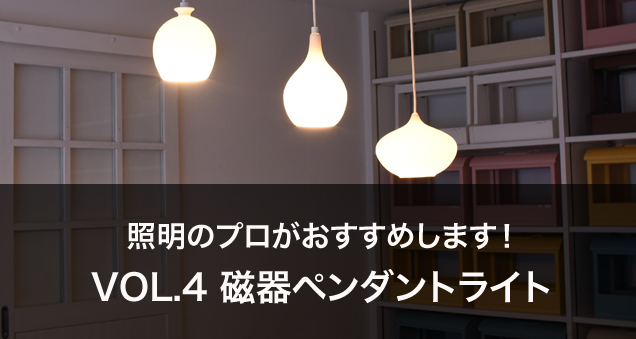
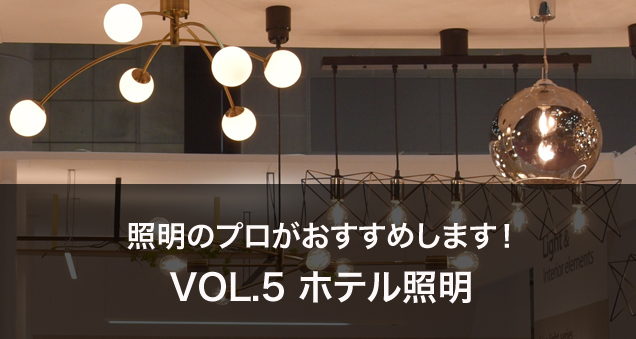
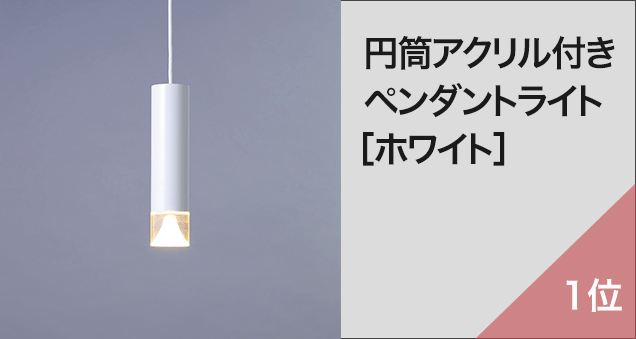
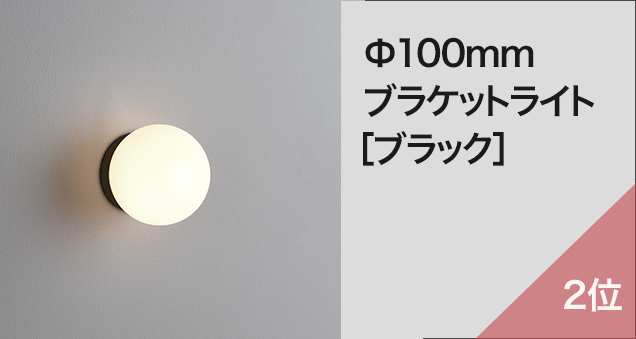
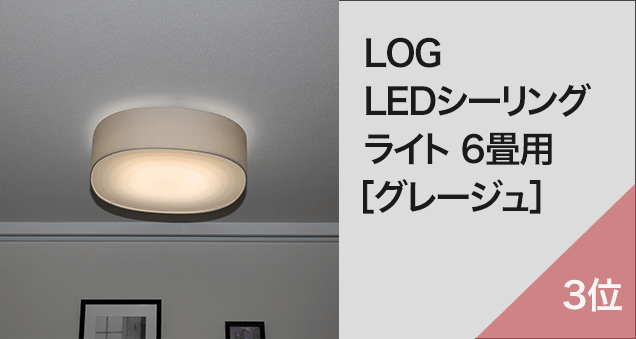
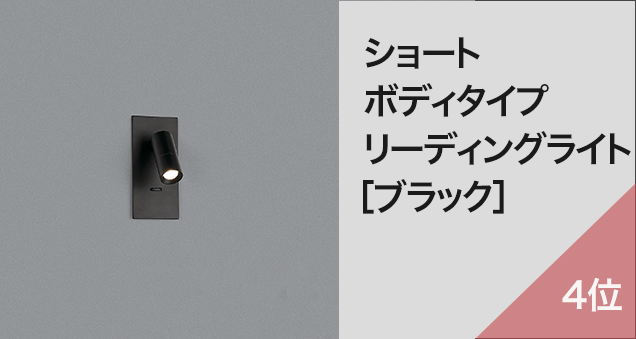



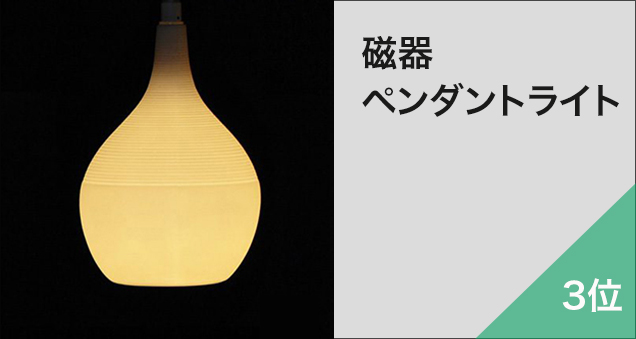

![[LEDペンダントライト/1灯] クリアランプのキラメキ感があそび心ある印象的な空間を演出。](https://www.motom-jp.com/wp-content/uploads/2020/07/motom-recommended-banner_2-05.jpg)